「各部門が独立して動いており、全社一体感が感じられない…」
「部門間の協力が少なく、個々の部門最適に陥っている…」
「他部門との連携を評価したいが、適切な方法がわからない…」
このような課題を抱える経営者や人事担当者は少なくありません。本記事では、部門間連携を促進し、組織全体のモチベーション向上を実現する評価手法について解説します。
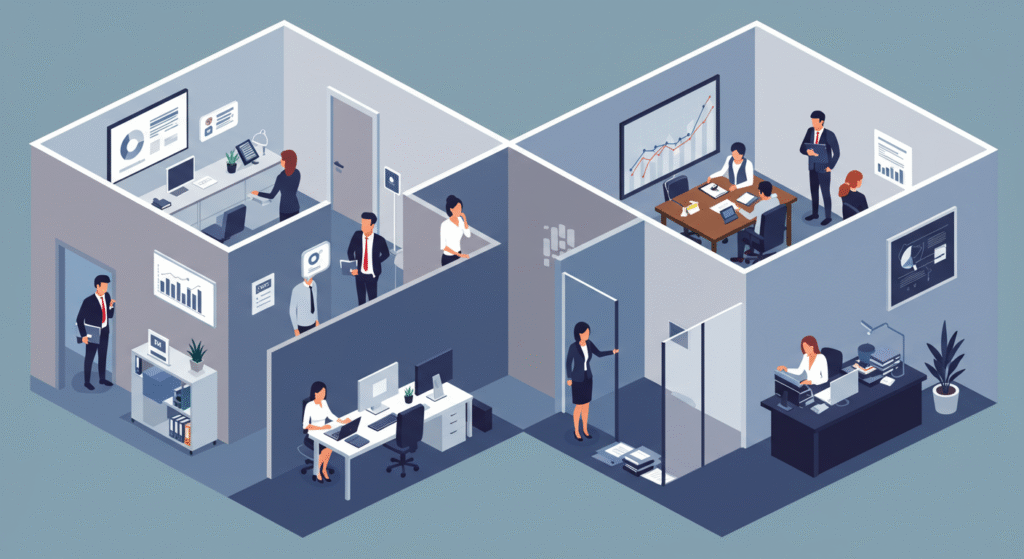
現代の多くの組織では、IT化や専門性の高度化に伴い部門の独立性が強まる一方で、ビジネスの複雑化により部門間の連携がますます重要になっています。しかし、実際には「サイロ化」と呼ばれる部門間の壁が形成され、組織全体の効率性や革新性を阻害するケースが頻繁に見られます。例えば、営業部門が製品開発部門と十分に連携せずに顧客との約束をしてしまい、後から実現困難な要求であることが判明するといった問題が典型的です。
部門間連携の不足は、社員のモチベーション向上を阻害する重要な要因となります。自分の仕事が他部門にどのような影響を与えているかが見えないと、業務の意味や価値を実感することが困難になります。また、他部門からの協力が得られずに目標達成が困難になったり、逆に他部門への貢献が適切に評価されなかったりすることで、不公平感や孤立感が生まれます。このような状況では、社員は「自分一人が頑張っても意味がない」「他部門の人たちは協力してくれない」といった否定的な感情を抱きやすくなります。
従来の人事評価制度では、部門内での成果や行動に焦点が当たりがちで、部門を超えた協力や貢献が十分に評価されていないケースが多く見られます。これにより、社員は自部門の利益を優先し、全社最適よりも部門最適を追求する傾向が強まってしまいます。「他部門のことは関係ない」「自分の部門の数字さえ達成すれば良い」という考え方が蔓延すると、結果として組織全体としての競争力が低下し、イノベーションの創出も阻害されることになります。
一方、部門間連携が活発な組織では、社員は自分の仕事がより大きな目的に貢献していることを実感でき、仕事の意味や価値を深く理解できます。他部門のメンバーとの協働を通じて新たな学びや刺激を得ることで、成長実感と達成感が高まり、結果として高いモチベーションを維持できるようになります。「自分の専門知識が他部門の課題解決に役立った」「他部門の視点を取り入れることで、より良いソリューションが生まれた」といった体験は、仕事への誇りと満足感を大幅に向上させます。
部門間連携によるモチベーション向上は、単に業務効率の改善にとどまらず、組織文化の変革と持続的な競争力の構築につながる重要な取り組みです。社員一人ひとりが組織全体の成功に貢献している実感を持てる環境を整えることで、内発的なモチベーションが高まり、より創造的で積極的な行動を促進することができます。これは、個人の満足度向上だけでなく、組織のパフォーマンス向上と長期的な成長にも直結する重要な要素です。
効果的な部門間連携評価の実践手法
360度評価(多面評価)による部門横断フィードバック

部門間連携を促進し、モチベーション向上を実現する最も効果的な手法の一つが、360度評価(多面評価)の戦略的活用です。従来の上司による一方向の評価に加えて、他部門のメンバーからのフィードバックを積極的に取り入れることで、部門を超えた貢献や協力を可視化し、適切に評価できます。
この手法では、各社員が関わったプロジェクトや業務において連携した他部門のメンバーから、具体的な協力内容や貢献度について詳細なフィードバックを受けます。例えば、営業部門の社員が製品開発部門との連携で顧客ニーズを正確に伝達し、製品改善につなげた場合、その貢献度を開発部門のメンバーが評価します。また、人事部門が現場部門の業務改善にどのような支援を提供し、どの程度の効果をもたらしたかを現場のマネージャーが評価するといった具合です。
重要なのは、この360度評価(多面評価)が単なる評価点の集計に終わらず、具体的な行動やその影響について詳細に記録されることです。「○○プロジェクトで、△△さんの迅速で正確な情報共有により、我々の部門でも適切な対応ができ、最終的に顧客満足度の20%向上につながった」「××さんの技術的アドバイスにより、営業提案の成約率が15%改善した」といった具体的なエピソードを蓄積することで、社員は自分の部門を超えた価値創造を実感できます。
また、360度評価(多面評価)を通じて他部門のメンバーと定期的にフィードバックを交換することで、相互理解が深まり、日常的な連携もスムーズになります。「あの部門の人たちも自分の仕事を理解してくれている」「自分の努力が他部門からも認められている」という実感は、強力なモチベーション要因となります。さらに、他部門の業務内容や課題を理解することで、より効果的な協力方法を見つけることができ、組織全体の効率性向上にもつながります。
部門横断プロジェクトでの共同評価制度
部門間連携を評価する効果的な仕組みとして、部門横断プロジェクトにおける共同評価制度の導入が挙げられます。この人事評価制度では、異なる部門から参加するメンバーが共通の目標に向けて協働する際の貢献度や協力姿勢を、プロジェクト全体の成果とともに包括的に評価します。
共同評価では、個人の専門的なスキルや直接的な成果だけでなく、「他部門のメンバーとの効果的なコミュニケーション」「異なる視点や価値観の尊重と活用」「部門間の利害調整における建設的な貢献」「全体最適を考えた判断と行動」「困難な状況での部門を超えたサポート提供」などが重要な評価項目となります。これにより、社員は部門の枠を超えた視点で物事を考え、行動することの価値を理解し、実践するようになります。
特に効果的なのは、プロジェクト完了後に全参加メンバーで実施する振り返りセッションです。各部門の代表者が、他部門メンバーの具体的な貢献や、協働を通じて学んだことを詳細に共有することで、相互の価値認識が深まります。「製品開発の技術的視点から営業戦略を見直すことで、これまでにない顧客アプローチを発見できた」「現場の生の声を直接聞くことで、人事制度の改善点が明確になり、より実用的な施策を企画できた」といった学びの共有は、参加者全員のモチベーション向上と今後の連携促進につながります。
また、プロジェクトの成功要因として部門間連携がどの程度寄与したかを定量的に分析し、その結果を評価に反映させることも重要です。連携によって生まれた付加価値、効率化の効果、コスト削減の実績、顧客満足度の向上などを具体的な数値で示すことで、社員は部門間協働の実際的な価値を理解し、今後も積極的に連携しようという動機が高まります。この定量的な成果は、経営層への報告や他のプロジェクトのベンチマークとしても活用できます。
部門間相互理解の促進と評価
持続的な部門間連携を実現し、長期的なモチベーション向上を図るためには、お互いの業務内容や課題、価値観、専門性を深く理解し合うことが不可欠です。この相互理解を促進し、評価する仕組みを整えることで、表面的な協力を超えた真の連携が可能になります。
具体的な取り組みとしては、定期的な「部門間交流セッション」の開催が効果的です。各部門が自分たちの業務内容、目標、直面している課題、他部門への期待や要請などを詳細に共有し、質疑応答を通じて相互理解を深めます。このセッションでの積極的な参加姿勢、建設的な質問、有益な情報提供、他部門の課題に対する解決策の提案などを評価項目に含めることで、社員の参画意欲が高まります。「今まで知らなかった他部門の苦労がわかった」「自分の部門が提供できる支援が明確になった」といった気づきは、その後の日常業務における協力関係の質を大幅に向上させます。
また、「部門間メンタリング制度」を導入し、異なる部門のメンバーがお互いの業務を理解し、知識やスキルを共有する機会を設けることも非常に有効です。この制度では、メンターとメンティーの両方を他部門から選び、定期的な面談を通じて相互の学びを促進します。例えば、経験豊富な営業担当者が製品開発の若手エンジニアにメンタリングを提供し、逆にエンジニアが営業担当者に技術的な知識を共有するといった相互学習が実現します。メンタリングの質や頻度、相互の成長への貢献度、知識移転の効果などを評価することで、部門を超えた人材育成への参画が促進されます。
さらに、日常業務においても他部門への配慮や協力を評価する仕組みを整えることが重要です。「他部門への情報共有の迅速性と適切性」「他部門の事情を考慮した業務進行」「部門間の課題解決への積極的な参画」「緊急時における部門を超えたサポート提供」などを継続的に評価し、フィードバックすることで、部門間の協力が日常的な行動として定着します。これらの行動を人事評価制度に組み込むことで、社員は部門間協力を「特別な取り組み」ではなく「当然の業務の一部」として認識するようになります。
部門間連携による組織文化の変革
部門間連携を重視した人事評価制度の導入は、単なる評価方法の変更にとどまらず、組織文化の根本的な変革をもたらします。従来の「部門の成功」を最優先とする文化から、「組織全体の成功」を共通目標とする文化への転換が図られます。この変革は段階的に進行し、最初は制度に従った行動から始まりますが、やがて社員の価値観や行動規範にまで浸透していきます。
この文化変革の過程で、社員は自分の仕事を「部門の一員」としてだけでなく、「組織全体の一員」として捉えるようになります。他部門の成功も自分事として考え、積極的に協力しようとする姿勢が醸成されます。「あの部門が困っているなら、自分に何かできることはないか」「このプロジェクトは会社全体にとってどのような意味があるのか」といった視点で物事を考えるようになり、より広い視野での判断と行動が可能になります。このような意識の変化は、個人のモチベーション向上だけでなく、組織全体の結束力と競争力の向上にもつながります。
また、部門間連携を通じて多様な視点や専門知識に触れることで、社員の視野が広がり、創造性や問題解決能力が向上します。「自分の部門では思いつかなかった解決策を他部門の人が提案してくれた」「異なる専門分野の知識を組み合わせることで、革新的なアイデアが生まれた」「他部門の成功事例を自分の業務に応用できた」といった体験は、仕事の面白さや意義を再発見する機会となり、内発的なモチベーション向上につながります。
さらに、部門間連携が活発になることで、組織全体の学習能力が向上し、変化への適応力も高まります。一つの部門で得られた知見やノウハウが他部門でも活用されることで、組織全体のナレッジベースが蓄積され、継続的な改善と革新が促進されます。このような学習する組織の実現は、社員にとって「自分が成長できる環境」「新しいことを学べる場所」として組織を認識させ、エンゲージメントの向上にもつながります。
テクノロジーを活用した部門間連携の促進
現代の部門間連携においては、適切なテクノロジーの活用が不可欠です。YELL BASEのような統合的な評価支援システムは、部門を超えたフィードバックの収集と分析、部門横断プロジェクトの進捗管理、相互理解促進のためのコミュニケーション支援など、部門間連携に必要な機能を包括的に提供します。
特に効果的なのは、日常的な部門間協力を可視化し、リアルタイムで認識する機能です。他部門への協力や情報共有、問題解決への貢献、知識の提供などをシステム上で記録し、定期的にフィードバックすることで、部門間連携が継続的に促進されます。社員は自分の部門間協力の実績を確認でき、他部門からの感謝のメッセージや評価も受け取ることができるため、協力することの価値と意義を実感できます。
また、360度評価(多面評価)のデジタル化により、物理的に離れた部門間でも効率的にフィードバックを交換でき、より包括的で客観的な評価が可能になります。システムを通じて収集されたデータは分析され、組織全体の部門間連携の状況や改善点を把握することができ、より戦略的な組織運営につなげることができます。
まとめ:部門間連携による持続的なモチベーション向上
部門間連携を重視した人事評価制度は、社員のモチベーション向上と組織の競争力強化を同時に実現する効果的なアプローチです。360度評価(多面評価)による部門横断フィードバック、共同評価制度、相互理解の促進という要素を組み合わせることで、社員は自分の価値を部門を超えて認識し、より大きな目的に貢献している実感を得ることができます。
重要なのは、部門間連携を一時的な取り組みではなく、組織文化として定着させることです。継続的な評価とフィードバック、テクノロジーの活用により、部門の壁を越えた協働が日常的な行動として根付くことで、持続的なモチベーション向上と組織の発展が実現します。
部門間連携の推進は、単に業務効率の改善にとどまらず、社員の仕事に対する意味や価値の発見、成長機会の拡大、創造性の向上など、多面的なモチベーション向上効果をもたらします。組織全体が一つのチームとして機能することで、個人と組織の両方が持続的な成長を実現できるでしょう。
【お問い合わせ・資料請求】
株式会社ラフト
Email: info@raft-base.co.jp
360度評価(多面評価)の導入についてより詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。専門のコンサルタントが、貴社の状況に応じた最適な施策をご提案させていただきます。



